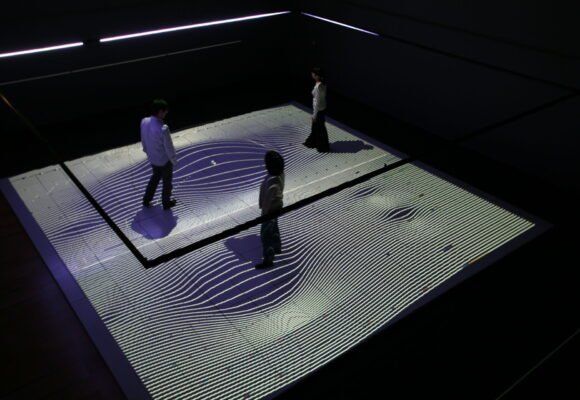文化研究者、実践女子大学准教授。単著に『現代美術史——欧米、日本、トランスナショナル』(中央公論新社、2019年)、『ポスト人新世の芸術』(美術出版社、2022年)。主な共著に『レイシズムを考える』(共和国、2021年)、『新しいエコロジーとアート——「まごつき期」としての人新世』(以文社、2022年)など。監修に『基礎から学べる現代アート』(亀井博司著、晶文社、2023年)。共編著に『この国(近代日本)の芸術——〈日本美術史〉を脱帝国主義化する』(月曜社、2023年)。1986年千葉県生。
視覚芸術の力を再認識する
侵攻が続く。パレスチナ・ガザ地区の話だ。ガザでの虐殺が目立つが、それ以外のパレスチナ(ヨルダン川西岸地区など)への侵攻も着々と進む。過去の話ではない。現在進行形の話だ。コミック・ジャーナリズムの第一人者として著名なジョー・サッコは、1990年代初頭からイスラエルのパレスチナ支配を追ってきた。邦訳もある『パレスチナ』(小野耕世訳、いそっぷ社、2007年/特別増補版、2023年)は、その代表作だ。
『ガザ 欄外の声を求めて』(早尾貴紀訳、Type Slowly、2024年)は、そのサッコの(パレスチナを扱った)二作目の著書だ。あらためて紹介すると。サッコは1960年にマルタ島で生まれたジャーナリスト。綿密な取材に立脚した戦争ルポルタージュ漫画で知られる。本書は、パレスチナで第二次インティファーダ(イスラエル占領地に住むパレスチナ人の抵抗運動)が勃発した2000年に計画され、2002年から2003年にかけて行われた取材に基づいて著された。だが、本書が照準を合わせるのは第二次インティファーダではなく、1956年のある出来事だ。
その出来事とは、同年にガザ地区南部に位置するハーンユーニスとラファハで発生したイスラエル軍のパレスチナ人虐殺を指す。サッコは、この出来事と当時も進行中だったイスラエルのパレスチナ支配を重ね合わせながら本書を構想している。その相似性、そして、さらにこの書評を執筆している時点(2024年)で起きている出来事との関連性については、本書の訳者でありパレスチナ/イスラエル研究を専門とする早尾貴紀の「訳者解説・あとがき」や、彼が『週刊金曜日』(2024年10月4日)に寄稿した論考(「繰り返される「テロリスト一掃」の名の下の虐殺 ジョー・サッコ『ガザ 欄外の声を求めて』を手がかりに」)に詳しいので、ぜひ一読してほしい。
私が専門とする視覚文化研究の観点からも、『ガザ 欄外の声を求めて』は興味深い示唆を与えてくれる著作だ。まず、本書は視覚芸術のもつ力をあらためて浮き彫りにする。細部まで描き込まれた人々の表情や、その人たちがまとう衣服や使用する物のひとつひとつが、ときに言葉よりも雄弁にパレスチナ(ガザ地区)の現状を物語る。サルトルやレヴィナスを引くまでもなく、人々の個別性や特異性の象徴である「顔」は、私たちに倫理や責任を要請するものだ。本書に登場する無数の異なる顔、顔、顔。その表情を前にして、私たちは自分にできるアクションを起こすこと、その一歩を踏み出すことを強く求められる。
同時に、『ガザ 欄外の声を求めて』は、虐殺や圧制を描く場面では、そうした個別の顔が単なる「物」のように無個性なものとして扱われてしまうことの恐ろしさも実感する。そうした抑圧の場面が大型本の見開き1ページを使って描かれているのを目にするとき、逆説的な意味でも、私たちは視覚芸術の力を再認識することになる。言葉では言い尽くせないことでもあるので、ぜひとも本書を手に取ってみていただきたい。
早尾も訳者の一人を務めるサラ・ロイ『なぜガザなのか パレスチナの分断、孤立化、反開発』(岡真理+小田切拓+早尾貴紀訳、青土社、2024年)は、50年以上に及ぶ占領と封鎖のなかでパレスチナの人々が受けてきた構造的な暴力と恒常的な排除を明らかにする重要著作だ。異なる専門性をもつ岡、小田切、早尾がそれぞれの視点から加えた解説も学びの大きいものとなっている。なかでも、アラブ文学を専門とする岡が寄稿した解説に、この書評の文脈で興味深い証言が登場する。それは岡が2014年にガザ地区に入域したときのことを語る部分で現れる。彼女はこう書く。「(前略)現地に入って思い知ったのは、封鎖がまさしく構造的暴力であるがゆえに、その暴力性は、すぐにそれとわかるような目に見える形で存在してはいないということ、封鎖とは、『不可視の暴力』であるということだった」(312ページ)。
ここで岡が示唆するように、ガザではイスラエルの人々とパレスチナの人々は等しい「可視性(visibility)」を与えられていない。数多くの視覚文化研究が明らかにしてきたが、芸術の領域で、長らく男性は「見る(描く)主体」、女性は「見られる(描かれる)客体」として固定化されてきた。支配する(優位に立つ)側は見られることなしに自由に見ることができ、支配される(劣位に置かれる)側は見ることもできず、自らの力で見られる存在になることも困難な状況を強いられるのだ。すなわち、可視性(の度合いやそれへのアクセシビリティ)は権力関係と深く結びついている。『ガザ 欄外の声を求めて』の端々に詳細に描き込まれた監視カメラや検問所といったシステムは、まさに可視性をコントロールする装置(の一部)に他ならない。[1]私たちが本書から読み取ることのできる情報は、かように膨大だ。
エドワード・サイードやエラ・ショハットらが示してきたように、文化や芸術は独自の抵抗の力を備えているし、事実、文化や芸術は様々な仕方で歴史的に権力に対する抵抗を組織してきた。サイードの『文化と帝国主義』(大橋洋一訳、みすず書房、1998年)やショハットとロバート・スタムの共著『支配と抵抗の映像文化 支配と抵抗の映像文化』(早尾貴紀監訳、内田(蓼沼)理絵子・片岡 恵美訳、法政大学出版局、2019年)は、日本語で読むこともできる。『ガザ 欄外の声を求めて』もまた、現在進行形の入植植民地主義(先住者がいる土地にしばしば暴力的に入り込み、その土地や資源を奪う形式でなされる植民地主義の一形態)の侵略に対する抵抗を形成する文化に連なるものだ。
カルチュラル・スタディーズの確立者の一人であるレイモンド・ウィリアムズが繰り返し強調していたように、文化とは本来「ふつうのもの」である。だから、誰もが文化を享受し続ける権利を有する。そして、こうした広い意味における文化のなかには、本来的に生命維持活動に直結するような「食文化」なども含まれる。文化が生存と深く結びつく大切なものである所以だ。しかし、ガザでは恒常的に文化が破壊され、可視性の権利と同様、文化へのアクセス権、自分たちの文化を保持し享受する権利、さらには食や生活といった生存のための文化すらも剥奪されている。私たちは誰にとっても「ふつうのもの」としての文化を連帯して死守しなくてはならない。
日々、ガザで、パレスチナで起こる「最悪を更新する出来事」は、私たちを無力感の奈落へと突き落とす。だが、それでもできることはあるはずだと信じたいし、そう信じることしか私にはできない。今起きていること、これまで起こってきたことを少しでも知ること、知ろうとすることは、そのひとつだ。それは無関心という内なる暴力に抗うことであり、目を背けて知らない振りをしていられる特権を手放すことだ。『ガザ 欄外の声を求めて』は、私たちが正しく歴史を知る手助けをしてくれると同時に、視覚芸術・文化の、その視覚性(visuality)の力を再確認させてくれる。本書が、芸術や文化に多様な仕方で関わるすべての人々にとって必読文献たるゆえんだ。
[1] 未邦訳だが、Gil Z. Hochberg, Visual Occupations: Violence and Visibility in a Conflict Zone (Duke University Press, 2015)は、こうした可視性のコントロールがパレスチナのイスラエル占領地域でどのようになされているかについて、現代アートや映画を題材にして論じた重要な文献である。
INFORMATION
『ガザ 欄外の声を求めて』
著者:ジョー・サッコ
訳者:早尾貴紀
ブックデザイン:勝浦悠介
発行:合同会社Type Slowly