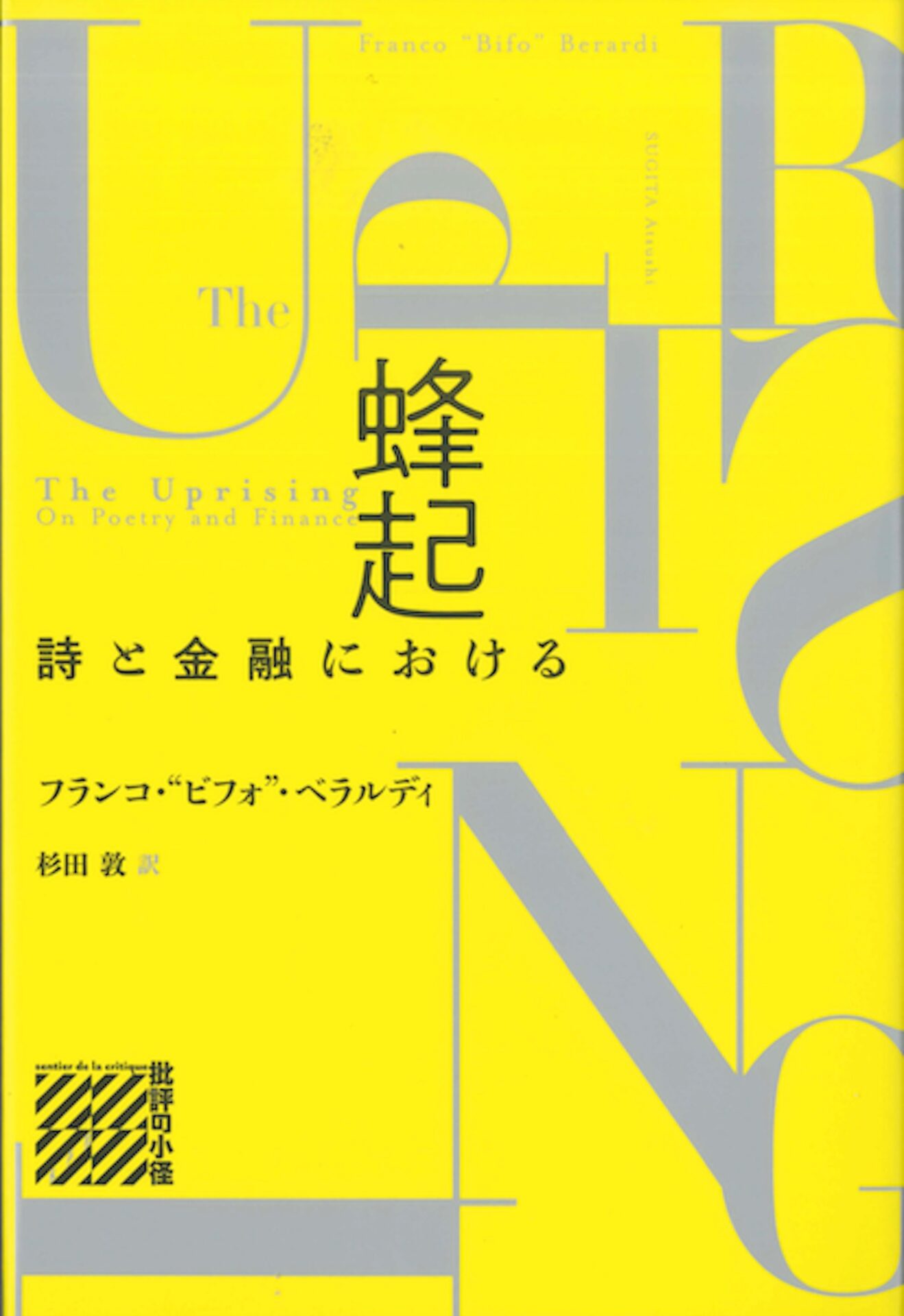「アーティスツ・ユニオン」という、日本のアーティストによる労働組合を筆者は昨年、仲間とともに作ったのだが、なぜ今ユニオンなのか、ということに関し充分に言語化できていないのではないか、という思いがあった。むろん、アーティストの労働者としての活動環境が劣悪であること、労働者なら当然ながら享受できるはずの権利、つまり働いたら報酬を受け取る権利、労災に遭った場合に補償を受ける権利、ハラスメントのない環境で働く権利、が現在の日本においては保障されていないこと、が大きな動機となった。だが、筆者の住むフランスにおいてはすでに半世紀も前に結成されているアーティストのためのユニオンが、今なぜ日本においてその気運が高まったのか? さらには、アーティストによるユニオンの結成にとどまらず、アーティストによる労働運動が今世界的な広がりを見せている。つまりさまざまな形で「蜂起」が起きているが、それはなぜか?ということに関して、本書はヒントをもたらしてくれたように思うので、それを共有したい。
『蜂起―詩と金融における』という本なので、「蜂起」を語るにあたり、まず「詩」と「金融」のパラレルな歴史に着目し、「言葉の世界」と「貨幣の世界」を相似形のものとして捉えるところから始まっている。「言語の過剰としての詩」と、「貨幣を過剰に抽象化した結果としての金融」はどう繋がっているのか。
言葉と意味が一対一で対応している状況において、つまり言葉が物理的世界にあるものを一対一で指し示している状況、これを「インデックス化」と呼ぶ。一方で、貨幣の世界においては、貨幣が一定量の物理的な商品と交換可能な状況がある。これも「インデックス化」と呼ぶことができる。
言葉―モノー貨幣がすべてそれぞれ一対一で対応している世界、というのは大変理解しやすいが、現在私たちが生きている世界というのはそんなに単純なものではない。言葉とモノが一対一に対応しなくなる状況、これを「脱インデックス化」というが、これがまさに、20世紀の詩的探求の賜物であった。著者の持論によれば、ランボーに代表されるようなフランスおよびロシアの象徴主義の詩人たちの実験が言葉とモノを一対一の対応関係から切り離したことが、経済が金融化する時に生じる、モノと貨幣の一対一の対応関係の崩壊を予言していたというのだ。
著者はそこからさらに展開して、インターネットの検索エンジンにおける言語のインデックス化の過程における二つのアルゴリズムについて述べる。つまりグーグル検索において一つめのアルゴリズムにより単語の様々な出現箇所を見つけ出し、それを二つめのアルゴリズムにより(広告会社的な手法で、あるいはアマゾンのアフィリエイトのような手法で)金銭的価値に結びつけているのだ。そのような、インターネット上のアルゴリズムを通じた、言葉の意味を貨幣価値に変換したことによる富の蓄積は、当然の帰結として、権力の集中、さらには政治的な意思決定とも分かち難く結びついている。この本が書かれたのは2011年なのだが、その後、巨大IT企業への情報の一極集中は加速し、コロナ禍を経て貧富の格差はかつてないほど深刻化し、AIがいつの間にか日常生活の中にまで侵食して人々の個人情報を収集し続けている。これらのことは本書の中で予見されていたことの延長線上にあるだけでなくそれをさらに過酷にしたもののようにも思える。つまり、詩と金融は、きわめて今日的な問題の中核にあるというわけだ。
そして「蜂起」である。新自由主義改革による非正規雇用者の創出の帰結として、労組に守られていない、脱領域化された労働者が大量に生まれることになった。その当然の結果として貧富の差が拡大し、本来なら格差の是正に機能するはずの社会保障制度も焼け石に水、という状況において弱者が立ち上がるーそれが「蜂起」である。著者は2011年を蜂起の元年と位置付けているが、その具体的な動きとして挙げているのが、アメリカにおけるストライキや「オキュパイ」運動、ギリシア危機、スペインにおける「アカンパーダ」、ロンドンやローマにおけるデモの動き等々、であった。
金融資本主義とデジタルイノベーションが手に手を携えて出来上がったある種の植民地主義が支配的に広がる中、働いても働いても貧困の出口が見えない世の中で希望を見出すにはどうしたら良いのか?
著者は下記のような興味深い調査結果を挙げている。「大人になったときに何をしていたいか?」と尋ねられたドイツの若者のうち、4分の1が、アーティストになりたいと答えたのだというのだ。それに関して著者である“ビフォ”は次のように述べる。「わたしは、彼らがアーティストになりたいと言っているのは、アーティストであるということが、悲しい未来から逃れることを、悲しみとしての不安定な未来から逃れることを意味しているからだと考えている。彼らは、信仰を捨て、資本主義の未来が提示するものに対して期待することをやめさえすれば、不安定や悲しさも、別の何かに、それほど悲しくなく、不安定でない何かになると考えているのだ。」
つまり著者は、アーティストとして生きることを、定量可能な物理的な世界から遊離して、貨幣が貨幣を生む金融資本主義に支配された世界から解放された場所に生きる方法のひとつとして考えているのだ。
ここで、著者のフランコ・“ビフォ”・ベラルディがどういう人物なのかを振り返ってみたい。イタリアの哲学者だが、まず“ビフォ”というのは彼がイタリアの左翼運動において活動家であった際のコードネームで、一時期当局に拘束され釈放されたのちも、その頃の記憶を留めておくべく使い続けているものらしい。
“ビフォ”がアート界で知られているのは、2017年のドクメンタにおける反ユダヤ騒動における一件によるところが大きい。詳細は訳者の杉田敦さんのあとがきに譲るが、5年に一度行われるドクメンタでは、政治的なテーマを扱った作品が珍しくないが、彼の企画したイベントに対して反ユダヤ主義団体から糾弾があり、“ビフォ”の対応の仕方も話題となった。
ここで、さきほどの「言葉の世界」と「貨幣の世界」を相似形とする話に一度もどる。もし言葉とモノが一対一の対応から脱却したきっかけが、20世紀の象徴詩だったとしたら、モノと貨幣が訣別した契機はニクソン・ショック、つまり基軸通貨のドルと金を固定相場で交換可能としていたブレトン・ウッズ体制のからの脱却と言えるだろう、と著者は指摘している。金本位制の一種であるこの体制が崩壊したことで、貨幣価値が金という物理的な貴金属から解放され、記号的な金融経済への道筋が拓かれたのだ。
この現象と相似形に思えるものがアートの分野にあるとしたら、それは「レディ・メイド」の登場ではないか。デュシャンは、工業製品の便器を展覧会という文脈に置くことによりモノを本来の機能/意味から解放し、芸術作品とした。必ずしも作家が自らの手で制作した一点物でなく、大量生産された既製品であってもレディ・メイドとして芸術作品になりうる時代が到来したのだ。そこから、現代美術というものがはじまるとともに、芸術作品の金融商品的な扱いを可能にする道すじがひらかれたと言える。
先述のドイツの若者たちが想定している「アーティスト」が具体的にどのようなものであるかは定かではないが、それになることでグローバル金融資本主義経済から解放されると彼らが考えているとしたらそれは大きな間違いである。なぜならアートこそ「なおさら」グローバル金融資本主義経済の大波に巻き込まれざるを得ないからだ。現代美術の作品は、短期間で価格が高騰する可能性がある商品として、投機的投資の対象となりやすい。
一方で、すぐに投機の対象とならなかったアーティストは、将来そうなるかもしれない、という不確定な未来の利益を担保にして、無償、あるいは不当に安い価格で作品の展示を要求されてきた実態がある。そのため生活のために多くのアーティストは非正規雇用に従事せざるを得ず、結果的には低賃金労働者として生きることになる。
著者はまた、グローバル金融資本主義の非実体的特性について述べている。敵もいなければ交渉する人間もいない、それこそがグローバル金融資本主義の特性であり、特定の個人や機関に収斂させることができないものだという。そのような実体のない対象への蜂起、に関して、彼は「詩」の持つ力について説く。同根の解放的性質を持ちながら、新自由主義のグローバル金融資本主義に対抗する手段として、言語の過剰である詩に可能性を見出そうと呼びかけているのだ。詩こそが、略奪的なグローバル金融資本主義によって蝕まれた社会的身体を再活性化する。
さらに蜂起そのものについては、あまりにも長いあいだ金融独裁が社会的身体を圧迫してきたため、それが暴力的な現象として立ち上がることは驚くに当たらないとしつつも、それは決して賢明ではないと断じている。蜂起は、社会的身体の病理に対する裁きの一形態なのではなく、癒しの一形態なのだ。さらにその癒しは、日常生活の中で連帯が再浮上するときにますます強化されると著者は主張する。金融資本主義に対する蜂起として、の詩と連帯。
「蜂起」―それがアート界において、あるいは日本においてどのような意味を持つのか、今まさに問われている。